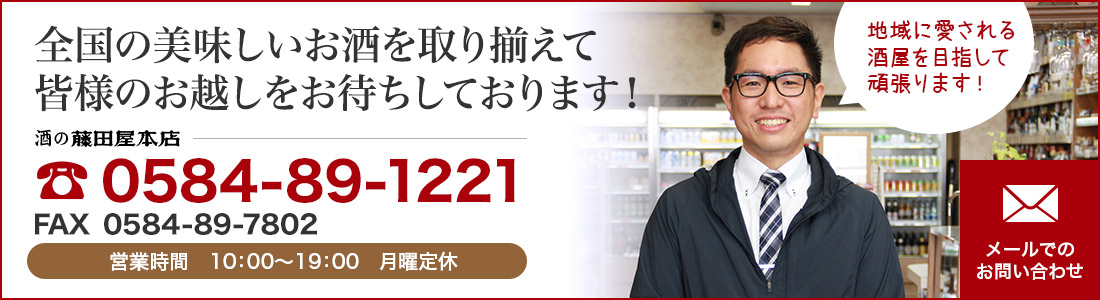ボッパルトの雫のニュースに想う「なぜ否認?ワインとGI制度」藤田屋 店長のつぶやき Vol.66
2025/04/25
カテゴリー店長のつぶやき
藤田屋 店長のつぶやき Vol.66
【なぜ否認?ワインとGI制度】
(↑画像生成AIで作った、白ワインとブドウ樹のイメージ図)
最近の、気になったニュース。
長年地域で愛されてきた青梅市のワイン「ボッパルトの雫」が、税務署の指摘で、ボッパルトの地名を名称に使えなくなったそうです。
長年地域で愛されてきた青梅市のワイン「ボッパルトの雫」が、税務署の指摘で、ボッパルトの地名を名称に使えなくなったそうです。
これを聞いて私(店長)は、なんとも複雑な気持ちになりました…
◆ボッパルトの雫とは?
本品は、青梅市と姉妹都市であるドイツ・ボッパルト市から贈られたブドウの苗木から生まれたワインです。
「ボッパルトの雫」の名は、両市の友好の現れだといえます!
毎年 飲むたびに、ボッパルト市を思い出す機会になる、良い商品だと思います♪
◆何が問題だった?
しかし、今回 問題になったのは、おそらくGI(地理的表示)制度。
地元産品の価値を守りつつ、消費者の誤認を防ぐための制度です。
国内でワイン名称に地名を入れるには、収穫と醸造を その地で行う必要があります。
本品は、青梅市で収穫したブドウを国内で醸造しているので、確かに基準外ではあるのです…
◆私の主観ではありますが…
「ボッパルトの雫」の名称は、両市にとって不利益はなかった気がします。
もしワイン産地としてボッパルト市が有名ならば、産地誤認は明らかな不利益ですが。
正直、そうではないと思うので、宣伝効果や友好関係の持続といった利益の方が、はるかに大きかったのではと。
ボッパルト市も、訴え出てはいませんし。
でも、GI制度のルールには反するため、認められなかったという…
私も普段は、GI制度は有用なものだと思っています。
こうした制度は、簡単には例外を作るべきではないのも分かります。
でも今回に限っては、本来は産地を守るための制度が、裏目に出てしまったように感じたのでした(ーー;
◆その後
青梅市では、本品の新名称を公募したそうです!
地名を使わずとも、両市の友好が思い浮かぶような、良い名称がつけばいいな、と思います(^^)
◆次回ご来店のとき「読んだよ」の声が聞けると嬉しいです!
—
【小さな「うれしい」「たのしい」「幸せ」をつむぐ】
藤田屋本店 <地酒とワインとお取り寄せ食品の店>
店舗 10:00~19:00(土日も営業・月曜定休)
岐阜県大垣市新田町3-8